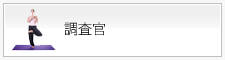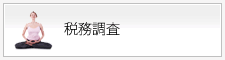税務署は準備調査を終えた後、どのようなことを行うのでしょうか?
税務署は準備調査を終えた後、実地調査・帳簿調査を行い、帳簿調査によって問題点が見つかった場合には反面調査を実施します。そして、問題点が何かあったときには、調査官は修正申告を提出するよう促します。
1.実地調査
準備調査は机上で行われますが、実地調査とは実際に法人に出向いて行う調査をいいます。
まず、代表者との面接を行い、会社の概要を聴取します。具体的には、会社の業務内容、会社の歴史、代表者の経歴、売上の計上方法、外注の決済方法等について、詳細に聞き取ります。
このような概況の聞き取りは、調査官にとって、一連の調査事務のうち最も大切な手続きであるといえます。概況をきちんと聞き取って会社の状況を理解しておかなければ、後に帳簿調査を行って疑問点が生まれても、もはや社長に聞けないということになりかねません。
納税者側は、質問事項について、誠意を持ち、ありのままを伝えることが重要です。作為的な説明をすると、後で矛盾が発覚しますし、このようなことをする必要は全くないといえます。誤解されないような丁寧な説明が、結果的には一番適切です。
調査官の質問検査は尋問ではないことから、受け答え時の納税者の表情から何かを洞察するといったことは通常考えられません。ただし、社長自身が売上を除外しているといった後ろめたいことを隠していると、おのずと表情に表れ、落ち着かない気持ちになります。ベテランの調査官なら、社長の動作から感じ取るものがあり、何気なく探りを入れ、見抜いていくことになります。このような事態を避けるために、日頃から適正申告を心がけることが、税務調査の正しく上手な受け方であるといえます。
調査官は、このようにして会社の概況を聞き取った後、帳簿調査を行います。
2.帳簿調査
帳簿調査とは、会社の元帳に計上されている各勘定科目の金額・内容を請求書・領収書と照らし合わせて調査することです。最も新しい決算期から目を通し、5期分さかのぼって調査します(5期分の調査を行うことについては、平成16年改正税法の附則に定めるところによるものです)。売上計上が適切か否かについては、売上の請求書の控えと売上帳の突合(とつごう)や、領収書の控えと入金額との突合により調査します。そして、不突合(ふとつごう)があれば、いわゆる売上除外が考えられます。仕入れや外注費に関しても、取引先からの請求書と仕入帳・買掛金台帳との突合を同じように行います。
3.反面調査
帳簿調査により問題点が見つかった場合については、仮に売上が計上されていないとしたら、相手先の会社に対して反面調査を行い、事実関係を確認します。
そして、本当に漏れているのであれば、決済方法の確認を行い、個人口座や簿外預金への振込み、小切手なら簿外口座での取り立て等を把握するよう努めます。具体的には、第一に取引先の法人に臨み、支払方法が振込み・小切手・手形のいずれによるものなのかを確認します。
振込みなら振込先の銀行にも臨み、その口座の入金内容を調査し、口座の名義人について、社長の個人名義の口座なのか、又は法人名義の口座でも法人の帳簿に記載のないいわゆる簿外口座なのかを、鋭く明らかにしていきます。これは、銀行調査と呼ばれます。
また、当該口座からの出金に関しても、銀行の出金伝票を調査し、振込出金ならその銀行に出向いて調べます。こうして不正計算が全体的に解明されていきます。
仮に反面調査を受けることになったとしたら、どうすればいいでしょうか。当局の捜査官への力添えが最も重要であるといえます。反面調査の拒否や非協力的な態度は、相手の不正計算に力を貸したと判断され、近い将来、自らが調査を受けることにつながります。このような事態を回避するためには、当局の反面調査に力添えするといいでしょう。
4.調査結果
問題点が何かあった場合には、調査官は修正申告の提出を求めます。このことを、修正申告を慫慂(しょうよう)すると呼びます。税務署から指摘のあった問題点に、納税者側が納得できず、修正申告の提出を拒否したときには、税務署により更正という行政処分が行われます。これに対して納税者側が納得できないなら、まず調査を行った当該課税庁に対する異議申立ての手続きをし、そこでなされた決定に不服があれば、国税不服審判所に不服申立てを行います。それでもなお納得できないなら、裁判に訴えます。
このような事態にならずに税務調査を終わらせることが大切なのですが、問題となっている案件に関して、どうしても考え方が一致せずに、国税不服審判所や裁判所に判断してもらおうと、不服申立てを行う場合があります。また、調査官の態度に満足できない、説得力のある説明がないといったことから、「修正申告を提出したくない。更正してくれ」と主張し、税務署長に対して異議申立てを行う例もあるようです。
修正申告書の提出については、最終期のみの修正でいい場合も、過去の事業年度にさかのぼる場合もあります。通常は最もさかのぼって5期ですが、不正計算があったときには7期さかのぼります。